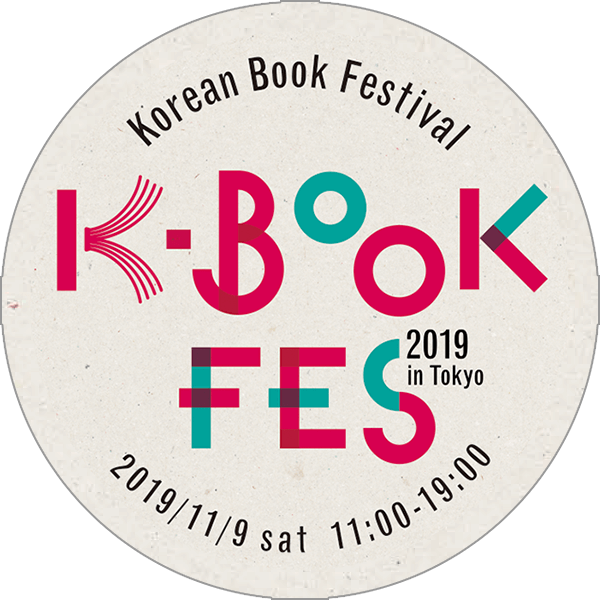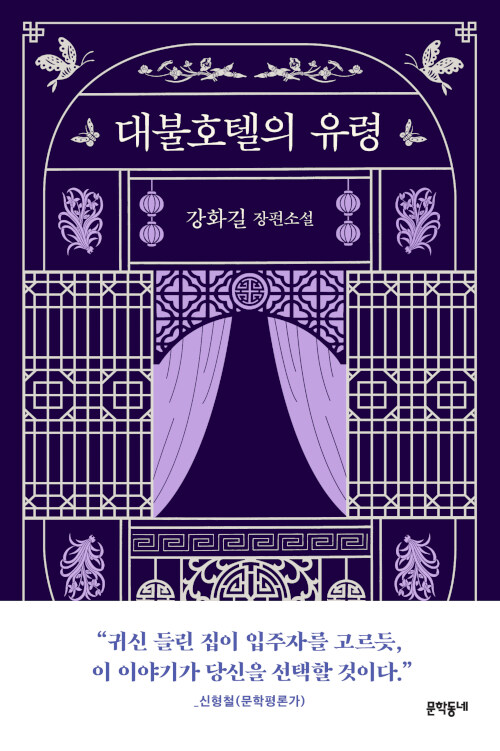
コロナ禍で日本から訪ねてくる人もおらず、私の住む町を案内して歩く楽しみもなくなってしまった日々。久しぶりに地方に住む知り合いが仁川にやって来たもので、私はいそいそと町案内に出かけた。
そして大仏ホテルの前に佇み、「ここは『大仏ホテルの幽霊』っていう小説の舞台になったの。面白いからぜひ読んでみて」と説明した。自分の住む町が描かれたこの小説を、ワクワクする思いで読んだ。
大仏ホテルは、朝鮮半島に初めて建てられた西洋式ホテル。長崎から渡ってきた堀久太郎が、1888年に建てた。福耳だった堀久太郎は「大仏さん」と呼ばれており、それにちなんで命名されたという。レンガ造りの3階立ては、当時、この辺りで一番高い建物だった。
鎖国をしていた朝鮮が、釜山、元山に次いで開港した仁川の港には、日本、清、西欧列強の船が次々とやって来た。大仏ホテルは開業当初、大いに繁盛したという。長い船旅に疲れた人々は、陸に上がる前から目についていた、このホテルを目指した。そこには白いシーツを敷いたベッドがあり、西洋料理もあった。
ところが1900年、朝鮮初の鉄道である京仁線が仁川からソウルの南大門まで開通するや、宿泊客は次第に減り始めた。ソウルに用のある人は、港に降りて1時間余り電車に乗れば、目的地まで行けるようになったからだ。
大仏ホテルは1918年に中国人に売却され、中華楼というレストランになった。その後、朝鮮戦争の戦火を逃れて運営されたが、老朽化して、1970年代に建て壊された。これが歴史に刻まれた史実だ。
私が8年前にこの町に引っ越してきたとき、大仏ホテル跡はまだ更地だった。その後、仁川市中区庁が昔の形を模して再築し、現在は区の運営する展示施設となっている。
しかし、大仏ホテルが中華楼になってからの歴史は、ほとんど知られていない。「中華楼」と漢字で書かれた看板が掲げられた、古い写真が残っているだけだ。朝鮮戦争後にここは、どのように使われたのか。空白の時間が、この小説の中にたっぷりと描かれている。
もちろん、これはフィクションだ。そうと知りながら、それでも過ぎた時間をたどるような思いでページを繰った。恐ろしげなタイトルが示唆するものはなんだろう。もしかしたらこの地には、だれかの怨念が宿っているのだろうか……。
主人公の女性は小説家で、新しい小説を書こうと苦悶している。不安にさいなまれ、耳の奥では「どうせおまえには書けない」という声がこだまする。
蘇る幼いころの恐ろしい思い出。自分は知らず知らずのうちに、だれかの恨みを引き受けてしまったのだろうか。精神科医の治療を受けても、症状は好転しない。
そんな主人公が母の親友ボエに誘われて仁川のチャイナタウンに出かけ、ボエの息子ジンと意気投合した。
ボエの父は、仁川に住む華僑だったという。ボエの母は主人公に、中華楼の怪談話を聞かせる。しかしその話は真実なのか。話者が変われば、過去の物語は反転する。物語は、ジンの家族史にも深く関わっている。「おまえは今度こそ、すべてを失うのだ」。耳の奥で、悪意に満ちた声が響く。
ボエの母の話に登場するのは、アメリカに渡ることを夢見るヨンジュ、戦火で家族を失ったヨンヒョン、中華楼を任された華僑のレイハン、そしてアメリカ人の小説家シャーリーだ。4人は中華楼の看板の掲げられた、かつての大仏ホテルで暮らしている。
p145 この大仏ホテルと中華楼を嫌う人々が、押し寄せてきた。私には初めて経験することだった。ヨンジュは二度、レイハンは数え切れないほど経験していた。今は1955年なのに、清の人たちの店に石を投げる韓国人はまだいた。地元意識を振りかざして怒る人々が、まだいた。彼らはテーブルや取っ手を壊した。従業員を殴り、悪態をついた。警察はそういう事件には大きな関心を持たなかった。だから彼らはたちの悪い蛮行が終わるまで、隠れて待つしかなかった。……汚いチャンコロめ、チャンコロに引っ付いた奴らめ、俺たちの場所を奪う、汚い凶悪な奴らめ!
1950年代のこの町には、人々の悪意や恨みつらみが満ちていた。
侵略者だった日本人は姿を消したが、今度は同じ民族同士の戦争が始まった。共産主義思想を学んだ者たちは、労働者の権利を唱えて人々を煽動した。それまで仲良く暮らしていた月尾島の人々は突然、右翼と左翼とに分かれて、激しい憎しみ合いが始まった。
p168 9月10日、爆撃があった。青年団の半分以上が死んだ。警察官の弟は斧を手に取った。世の中がまた変わってきたと感じたようだ。同時にそれは、腹いせのためでもあった。彼の家族は全て、爆撃で死んだ。まだ若い妻、2歳になったばかりの息子も犠牲になった。米軍の落とした爆弾は飛び散った。彼は叫んだ。これは、おまえらアカの奴らのせいだ。兄貴の仇をうってやる。俺の家族の恨みを晴らしてやる。皆殺しにしてやる。なんでお前らが生き残ってるんだ! 彼は斧を振り回した。表札を斧で切りつけた。生き残った青年団のうち、二人が死んだ。その5日後、米軍が仁川に上陸した。彼は青年団の家族を軍に引き渡した。彼はしつこかった。この町のだれが、隠れている青年団に米を一握りやったかまで調べ上げ、一人残らず捕まえた。そして彼は、港の近くに居所を移した。舟で逃げようとするアカを捕まえるためだった。
戦火の中で生き残った少女はヨンヒョンではないと、警察官の弟が証言する。では彼女は死者に成りすまして、いったいなにを企んでいるのか。
アメリカ人作家の心をつなぎ止め、自分もアメリカに渡ろうと企むヨンジュは、古い建物に悪霊が宿っていると言って、人々を恐怖に陥れる。
華僑だからと差別されるレイハンは、なぜアメリカに移民せずに韓国に留まろうとしたのか。
母の話が真実かどうか。そして母はなぜ自分を憎むのか。ボエの心には、次々と疑問が湧き起こった。
幼いころのボエは、母の話をそのまま信じていた。しかし父レイハンの死後、父を知る周囲の人々に話を聞くうちに、母の話とはまた別の物語が存在することに気づいた。
ボエは主人公に言う。
p252 面白いでしょ。だれかがだれかを疑い、憎み、そして死んで、逃げて……。だれかを傷つけたい心って、どうしてこんなに共感しやすいのかしら。話を信じたというより、理解したという方が当たってるのかもしれない。
エピローグには、ようやく自分の小説を書きあげた主人公がいる。
P301 私は毎日少しずつ、前に進むことができた。結局、物語を書くことは、生きていくのと同じようなことだ。毎日できることをしながら、生き続けていくこと。人生とはそんなふうに、続いていくという事実を受けとめること。その生を大切に思うこと。その心が再び、物語を書けるようにしてくれるのだと信じる。
でも実は、今もときおり、声が聞こえる。自分を踏みつけてしまいたくなる衝動を感じる。それは私自身の衝動かもしれない。でも私は、その声をそのまま聞いている。そして忘れる。忘れようと努力する。それが今の私の生だ。これからもそんなふうに、生きていこうと思う。
他人の不幸は蜜の味と思う人々がうごめいている世の中。他人に対する悪意はさらなる悪意を生み、怨恨の連鎖は轍となって、絡まり続けてゆく。だれもが自分を正当化し、自分なりの物語を紡いで生きているのだ。
小説の中には、関係ない場所、つながりのない時間に、いくつもの伏線が存在する。様々な疑問が終盤に向けて、はらりはらりとほどけていく心地よさ。だから韓国小説って面白いのよね!と拍手したくなる、良質のエンターテインメントだ。
私の住む仁川の町には、過ぎ去った人々の思いの宿る建物が、数多く残っている。騒乱や激動のどんでん返しを幾度も経てきたこの町には、数え切れないほどの物語が、今も息を潜めているに違いない。そんな町に暮らすことは、なんて幸せなんだろう。
この次にだれかを案内する機会があったら、私は大仏ホテルの前に佇んで、「実はここ、幽霊が出るのよ」と、怪しい笑みを浮かべて見せたい。そうして鞄の中からおもむろに、この小説を取り出して見せよう。町歩きの楽しみが、また一つ増えた。
戸田郁子(とだ・いくこ)
 韓国在住の作家・翻訳家。仁川の旧日本租界地に建てられた日本式の木造町屋を再生し「仁川官洞ギャラリー」(http://www.gwandong.co.kr/)を開く。「図書出版土香(トヒャン)」を営み、口承されてきた韓国の民謡を伽倻琴演奏用の楽譜として整理した『ソリの道をさがして』シリーズ、写真集『延辺文化大革命』、資料集『モダン仁川』『80年前の修学旅行』など、文化や歴史に関わる本作りを行っている。
韓国在住の作家・翻訳家。仁川の旧日本租界地に建てられた日本式の木造町屋を再生し「仁川官洞ギャラリー」(http://www.gwandong.co.kr/)を開く。「図書出版土香(トヒャン)」を営み、口承されてきた韓国の民謡を伽倻琴演奏用の楽譜として整理した『ソリの道をさがして』シリーズ、写真集『延辺文化大革命』、資料集『モダン仁川』『80年前の修学旅行』など、文化や歴史に関わる本作りを行っている。
朝日新聞GLOBE「ソウルの書店から」コラムの連載は10年目。著書に『中国朝鮮族を生きる 旧満洲の記憶』(岩波書店)、『悩ましくて愛しいハングル』(講談社+α文庫)、『ふだん着のソウル案内』(晶文社)、翻訳書に『黒山』(金薫箸、クオン)『世界最強の囲碁棋士、曺薫鉉の考え方』(アルク)など多数がある。