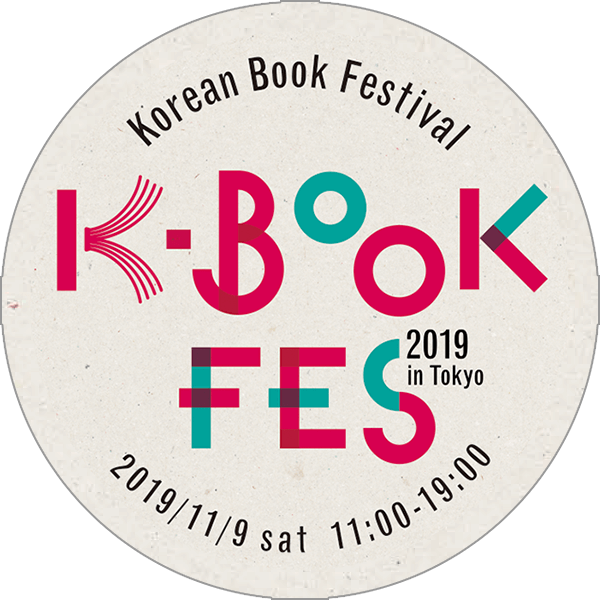没後十年が過ぎた現在も、韓国で国民的作家として愛され続けている朴婉緒(パク・ワンソ、1931〜2011)の自伝的長編二作品が、一冊の新訳書として刊行されました。
日本による植民地支配の時代、朝鮮の伝統的な暮らしが残る開城近郊の農村で少女時代を過ごす主人公。女性の自立を志向する母の教育方針に従い、ソウルで教育を受け、解放後の1950年、ソウル大学文理学部に入学するも、その年の6月に朝鮮戦争が勃発します。統治者が4回も入れ替わる過酷な状況下のソウルで兄と叔父を失いながらも、家族を守って懸命に生き抜く一人の女性の姿を描いた本作品は、500頁に及ぶ大作でありながら、全編にわたり作家自身が経験した「生々しい記憶の空間」を次世代に伝えたいという強い意志が流れ、一気に読ませる迫力に満ちています。
新訳では、日本語母語話者の真野保久氏と、韓国語母語話者の朴暻恩氏(I部)、李正福(II部)とのあいだで、韓国語ならではの表現を日本語としてどう表現するかについて議論を重ね、朴婉緒の世界が日本語で表現されている点も注目されます。
朝鮮戦争休戦協定から70年となる今年、韓国文学の源流ともいえる、終わらない戦争と女性の生き方を読み解くことができる作品です。(作成:中村晶子)
翻訳者を代表して真野保久さんから推薦コメントをいただきました。
「私の人生は平凡な個人史かもしれないが、いざ広げてみると荒々しく織りこまれた時代の横糸のせいで、自分の望みどおりの模様を織りこめなかった」――韓国の女性作家・朴婉緒は自伝的小説『あの山は本当にそこにあったのか』序文でこう記しました。
日本の植民地期の1931年に両班家に生まれ、開城近郊の田園地帯で心豊かに過ごした幼年期から、集落の若者たちからの襲撃に遭った日本の敗戦・解放時、そしてとくには統治者が3か月ごとに交代する朝鮮戦争下ソウルでの飢えと、北へ南へと避難を強いられた緊張の日々――。これらの時代を婉緒は、家長としての母、もの静かで秀才だった兄と義姉、その他の家族それぞれの変化とともに見つめ、子細に描き出します。
怒涛の日々を家族と共に、また家族であることの葛藤をものりこえたとき、婉緒は”自立”をはたすのです。
(真野保久)
『あんなにあった酸葉(すいば)をだれがみんな食べたのか/あの山は本当にそこにあったのか』(朴婉緒/著、真野保久・朴暻恩・李正福訳、影書房)