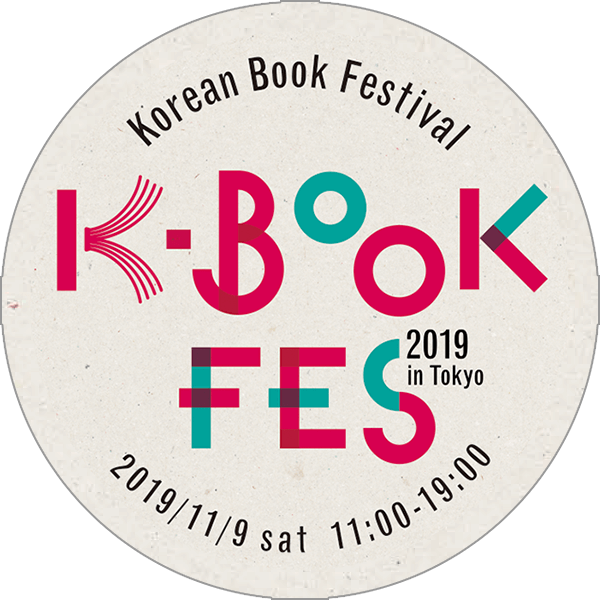【書肆侃侃房賞】
森川 裕美さん
『惨憺たる光』
暗闇に差す淡い光、その中に見えるもの

異国にあるときのような心許なさが、全編を通して漂っている。慣れ親しんだ世界から切り離され、社会的立場や役割もはぎとられ、裸の自分がむき出しにされているような、あの感覚。
『惨憺たる光』は十編からなる短編集で、すべての物語に異国が存在する。ロンドン、パリ、ヴェネチアなど欧州の都市が舞台だったり、ロッテルダムに暮らすおばの隠し子や華僑の義祖母、フランス人映画監督といった異文化を内包する存在が登場したり。
まっさらなまま向き合うとき、そもそも他人を理解することなんてできないという事実が、あらためて迫ってくる。本書の表紙にある、暗闇に差す淡い光と、その光に照らされた銀色の装身具。暗闇は、理解できない他人の内面。装身具が放つ弱々しい輝きは、ふとした拍子に一瞬だけ垣間見えるそのひとの何か。この物語には、その不確かで儚い一瞬が描かれている。
『北西の港』では、死期が近づく父の初恋の相手に会うべく、「僕」はハンブルグを訪ねる。女性の名はシム・スノク。想い合いながらも、彼女がドイツ派遣看護師に志願することになり、別れたのだという。
波止場をうろつき酒を飲んでばかりで家に寄りつかず、いつも母を泣かせていた父。父の代わりを自分に求めた母、母の差別に妬みの目を向けた姉たち。これまで一切家族を省みなかった父は、「何も見えない」と自分にすがり泣いた。父が大事にとっておいた手紙の束を発見し、「僕」はシム・シノクが愛した父を知りたいと思った。
会えたのはシム・シノクの娘ではなく、同じく派遣看護師だった韓国人の母を持つレナだった。レナの母はアルツハイマーを患い、記憶を失ったのだという。衰退してしまった故郷の港で、かつて口づけを交わしただろう若い男女。父が視力を、レナの母が記憶を失うだけの時間が流れた。長い歳月に渡り交わされた手紙の最後は、「あなたは私の知る最も孤独で、最も温かく、最も美しい人です」というシム・スノクの言葉で締めくくられていた。
本著が初邦訳作品となる、ペク・スリン(『82年生まれ、キム・ジヨン』と同い年だ)。何かしらの傷を抱え、静かに生きるひとびとを描く彼女の筆致は、どこまでも優しい。月夜の朧げな光が暗い水面に差しているように、ページをめくるごとに導かれ、彼らの内面に深く潜っていく。彼らの物語はかぎりなく静謐で、読み終えたあとに深い余韻を残す。そんな不思議な読書体験だった。