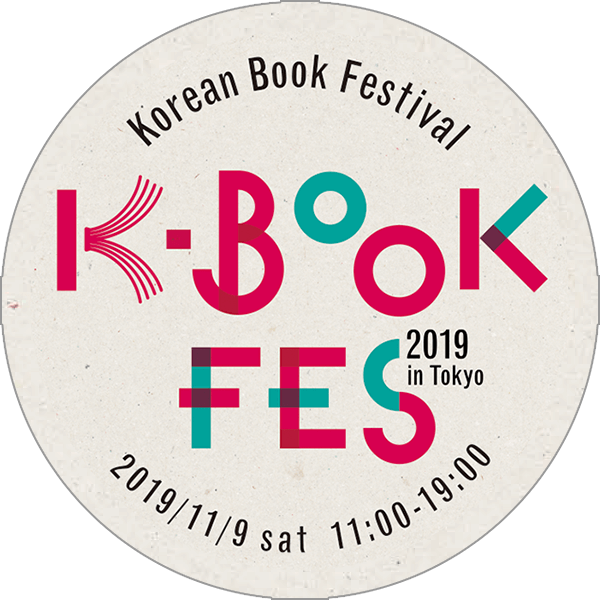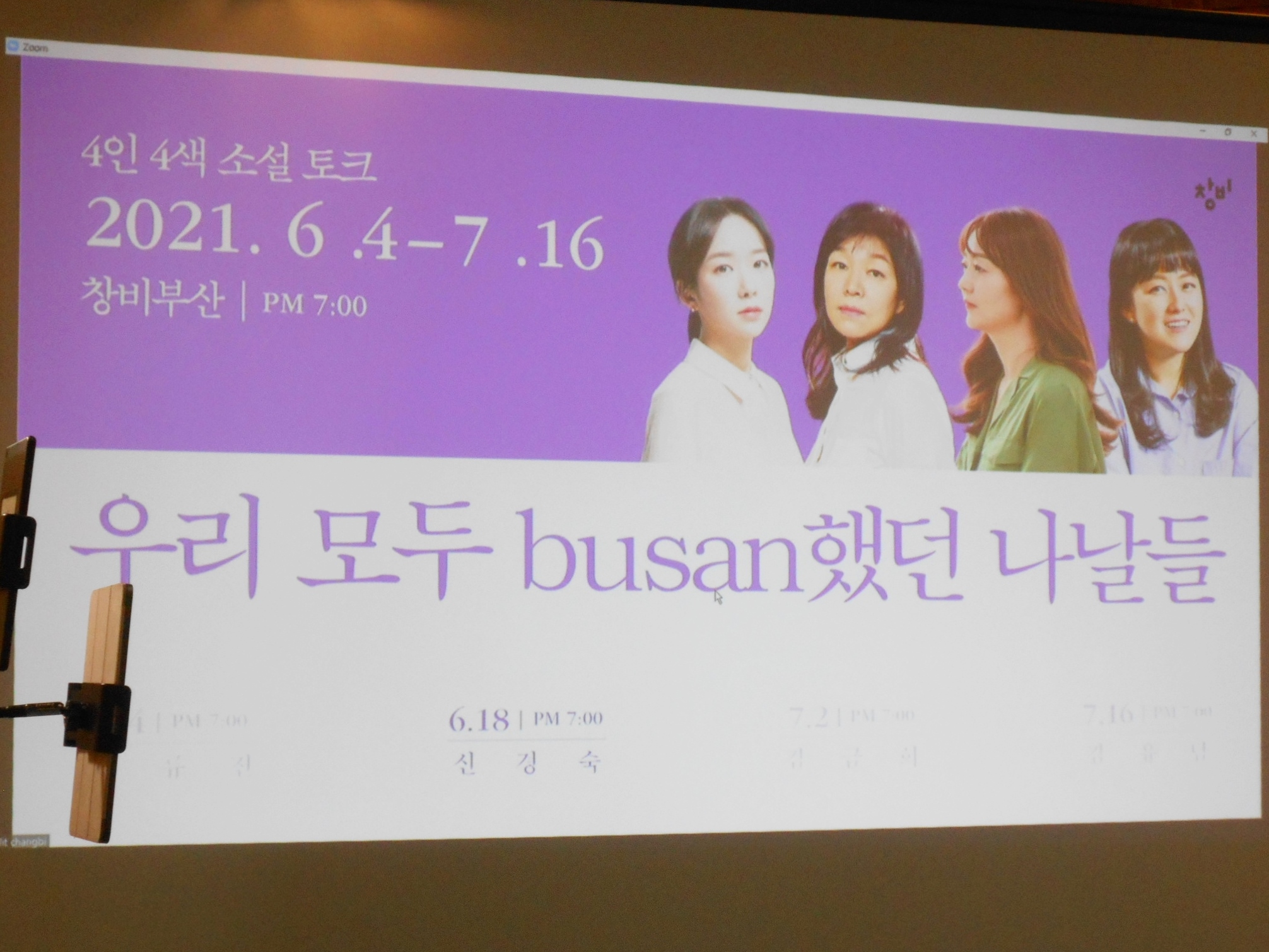
『母をお願い』(安宇植訳/集英社)などで日本でも広く知られる作家、申京淑(シン・ギョンスク)さんを招いてのトークイベントが6月18日、チャンビ釜山で開かれました。「4人4色 小説トーク」と題したリレートークの第2弾です。3月に刊行された長編『아버지에게 갔었어(父のところに行っていた)』を中心に文芸評論家ハン・ヨンインさんとの対談形式でおこなわれ、その様子はYou Tubeでも配信されています。
『父のところに行っていた』は幼くして両親を亡くし家長となった「父」が激動の時代を必死で生きてきたさまを、長女の「わたし」をはじめ周囲の人々との関係性を通して描いた物語です。以下、主なやり取りをご紹介します。


Q. 詩人、黄仁淑(ファン・インスク)さんがエッセイの連載コーナーにこう書いていた。「ギョンスクが6年ぶりに長編小説を出した。長くつらい時期を過ごしたあとに発表した作品なので、悪しざまに言う人がいなければいいがと心配していたが、杞憂だった。文章もストーリーもキャラクターも良いし、すらすら読めるのに胸にぐっとくる場面も多く、くすりと笑えるところもたくさんある。さらに円熟味が増した」。この応援メッセージ同様、新作を待っていた読者も多いと思う。この間どう過ごしていたか。刊行にあたっての思いも聞きたい。
A. ファン・インスクさんは五つ年上で同じ大学出身。私が文壇で唯一「オンニ(姉さん)」と呼ぶ存在だ。こういうことを書いていらしたとは知らなかった。この数年間、私は書くことや文学から離れていたわけではない。自分にとって書くこととは何かを考える時間だった。30代、40代を慌ただしく過ごすうちにおろそかにして壊れてしまったことを書き出して、一つひとつ修復させる時間を過ごしていた。なくしてしまっていた日常をしっかり踏みしめながら。こうして読者と対面するのは本当に久しぶりでうれしく、ありがたい。
Q. 『母をお願い』に続いて父についての話は書かないのかと聞かれるたびに「書かない」と言ってきた。その気持ちが変わったきっかけはベルリンのユダヤ博物館の展示物だったそうだが、具体的にはどういうことか。
A. 『母をお願い』はとても多くの方が読んでくれてうれしかった反面、作品があまりに遠くまで行ってしまった気がして不安や怖さもあった。大勢の人が読むことで小説の骨だけが残り、皮膚や肉、血などが全部なくなってしまう感じがした。それまでに経験したことのない大きな反響をどう受け止めればいいのか悩んでいたころだったので、「書かない」と答えていたように思う。
それから12年経って書くことになった具体的なきっかけは、ユダヤ博物館での経験だ。「落ち葉」という展示空間があり軽い気持ちで入ったが、心が凍りつくようだった。悲鳴を上げているような顔を模した無数の金属板が床を埋め尽くしていた。それらを踏んで奥まで歩いて戻ってくるのだが、一歩踏み出すたびに悲鳴のような金属音が響く。そのため先に進むのもためらわれ、かと言ってその場で顔を踏みつけたままでいるのもいたたまれない、という状況だった。そこを出たときに父の顔が浮かんだ。自分が長いあいだ父に対して抱いていた悲鳴のようなものが聞こえる気がして、韓国に帰ったら父の話を書こうと思った。
先ほども述べたように、自分がおろそかにしていた関係を修復させるために過ごした時間が5、6年あったが、その間、故郷の家もよく訪ねていた。ある日父に「いつか父さんの話を書くつもりだ」と話したら、父は驚いて「わしなんかの何を」と言った。私はその一言に衝撃を受けた。あれほど多くのことを成し、あれほどさまざまな経験をし、あれほど長い年月をくぐり抜けてここまで来た人が、わしなんかの何を、だなんて。その一言に胸が痛み、ずっと心に残っていた。ところが、いざ父を客観的に捉えようとすると、母のことは書きたいことが山ほどあるのに、父のことはどう書けばいいかわからなかった。一人の人間として見ず、単に「父親はこうあるべき」「父親とはこういうものだ」という概念としてしか見ていなかったことに気がつき反省した。そんなふうに考えるようになったのは、父がもう昔のように強い人間ではなく、人生のピークを過ぎ消滅直前の瞬間にいるからではないだろうか。それで勇気を出してこの作品を発表した。
Q. 終盤、父が「自分が死んだあと井戸を埋めないでくれ」と言う場面がある。「わたし」がそんなことは兄さんに言えばいいのにと答えると、父が「おまえは役に立たなくなったものも大事にする性分みたいだから」と独り言のように言う。小説全体を通して「役に立たなくなったもの」と「昔は大きな存在に思えたが、もはやそう感じられなくなった父」とは通じるところがあるようにも思えた。
A. 父を役に立たないと思ったことはない。もちろんそういう意味でおっしゃったわけではないことはわかっているが。人間も物も、役に立つか、立たないかに分けることはできない。ただ時代の流れの中で、今現在の価値基準でははかれなくなっていくということだと思う。この作品を通してわかったのは、この「父」は今この時代にまさに必要な存在だったんだなということ。たとえば「父」が自分の子どもたちに見せていた姿は、今、私たちが一緒に暮らしたいと思う、あるいは必要としている父親像であることに、書いていて気がついた。そういう父親は、昔は多かったと思うが、家父長制という巨大な枠でひとくくりにされるうちに観念的なものになってしまった。そういう「父」の些細な話一つひとつに耳を傾けたかった。
北野武監督があるインタビューで「家族についてどう思うか」と聞かれ、誰も見ていないときに捨ててしまいたい存在だと答えたそうだ。一理あると思った。家族として一緒に暮らしていて、いいことばかりのはずはない。時に傷つけ合いもするし、「ごめん」の一言が出てこないこともある。それが家族。私もそういう経験をたくさんした。誰もが一度はするそうした経験も含めて「父」の人生について考えるきっかけになったとしたら、これを書いた甲斐もあるというものだ。
Q. 非婚を選ぶ人が増えるなど、家族や結婚に対する感覚は過去とは大きく変わってきている。この作品からは、そういう流れに対する反発も感じられるような気がしたが。
A. 反発ではない。家族は必ずしも血縁で結ばれているべきとは思わない。ともに暮らすのが家族だと思う。ある空間で友人と暮せばその友人と家族の関係になる。ただ、同時に、こういう家族もいる、ということ。こういう表現は嫌いだが、自分を譲る一種の「犠牲の時間」を通過してきたからこそ現在があるとも思う。
だが、こうも考える。私は15歳まで田舎の村で過ごした。裕福な暮らしではなかったが、自分が冷たい場所に置かれていると感じたことは一度もない。貧しくても、親や村人など常に誰かが温かく見守ってくれる共同体があった。都会に出て40年以上になるが、つらいことがあっても再び前向きになれたのは15歳までの環境、経験のおかげだと思う。今の子どもたちもそういう経験をしてほしいと切に願う。
Q. 作品では自伝的な要素と創作の要素が混ざり合っていて、その境界はあいまいだ。読者としてはどこまでが事実でどこからが創作かが気になる。こういうスタイルを追求している理由は。
A. 特に追求しているわけではない。自分にとっては自然な書き方だ。『母をお願い』『離れ部屋』『父のところに行っていた』あたりの作品を読むとそう感じるかもしれないが、ほかにも百年前の話を書いたものなどさまざまな作品がある。そして「隠れる楽しさ」もある。読む人が事実だと思うような描写の中から自分を消したり、物語のあちこちに隠れたりもしてきた。ただ、21歳のデビュー当時からルールは一つある。もし誰のことか推測できるような人物を登場させるときは、絶対に悪く描かない。温かく、好感を与える人物として描けるときだけ実在の人物を持ってくる。事実と想像の世界を行き来する楽しみは、書く人にしかわからないと思う。

続いて、参加者とシン・ギョンスクさんによる朗読、質疑応答の時間がありました。昔からのファンだという人も多く、イベント終了後のサイン会では10冊近い著作を抱えてきた人も見かけました。
日本語で読めるシン・ギョンスクさんの作品は『母をお願い』のほかに『離れ部屋』(安宇植訳/集英社)、『山のある家 井戸のある家――東京ソウル往復書簡』(きむふな訳/集英社)、『月に聞かせたい話』(村山俊夫訳/クオン)などがあります。
「4人4色 小説トーク」第3弾(7/2)は5月に短編集『우리는 페퍼로니에서 왔어(わたしたちはペパロニから来た)』を刊行したキム・グミさんが登壇予定です。(文・写真/牧野美加)