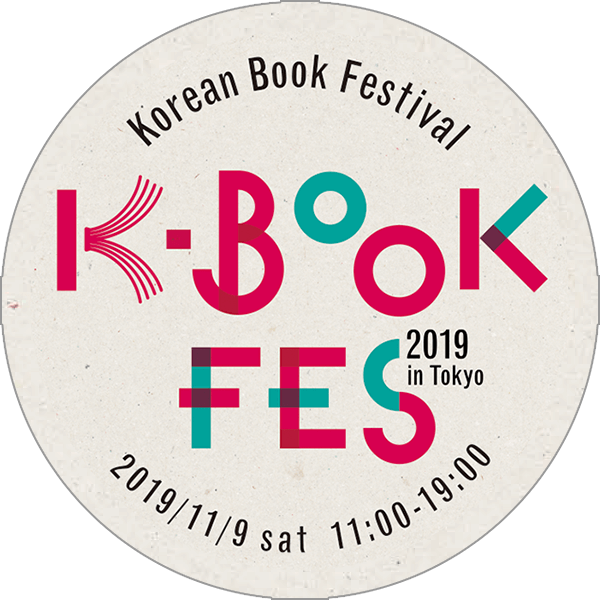韓国の詩人たちに最も敬愛されている詩人のひとりが白石(ペクソク、1912~1996)。1930年代後半から40年代前半に活躍した詩人で、解放後は故郷のある北朝鮮に残り、体制になじめずに筆を折りました。その筆を折る1962年までの最後の7年間を蘇らせた小説が『七年の最後』(キム・ヨンス著、橋本智保訳、新泉社)です。著者のキム・ヨンスは、現実のこの世で実現されなかったことは物語になり小説になると信じて、歴史からこぼれ落ちてしまった人間を主人公に様々な小説を書いてきました。「白石はなぜ詩を書くのをやめたのか、書く自由を奪われた詩人を生かし続けた力は何なのか、などの疑問」(訳者あとがきより)をきっかけに構想を考えはじめた『七年の最後』には、白石のほかにも近代朝鮮文学で活躍した詩人や小説家をモデルとした人物も多く登場します。その系譜につながる作家として生きているキム・ヨンスが、作家や詩人としての生を全うできなかった文学者たちを、自分の物語で生かしたかったのだろうと考えながら本作を読みました。キム・ヨンスによるフィクションの力と文章の美しさを存分に堪能できる作品です。訳者の橋本智保さんから推薦コメントを頂戴しましたので、ご紹介します。
構想に30年を費やしたという本書は、キム・ヨンスが多くの文献をもとに想像力を膨らませ、詩人白石の生きた世界をつくりあげたフィクションです。『夜は歌う』に続くキム・ヨンス文学の頂点にして、新たな創作の始まりを予感させる作品だと思います。
これまでのキム・ヨンスの小説は、歴史と個人史を絡み合わせることによって世界を理解しようとするものが多かったのですが、『七年の最後』にいたって少し変化が見られます。歴史の不条理を浮き彫りにし、その中で詩人はどう生きるのかについて語っているように思います。
白石は五十歳を目前にした頃、雪深い僻地に追いやられ、そのあとは筆を折ったと知られていますが、それは決して堕ちたのではなく詩人として生き抜いたのだと信じてやまないキム・ヨンスの「白石物語」が繰り広げられます。その物語のことばが仄かな灯りとなって、いまここで生きる私たちの心にも灯りますように。(橋本智保)