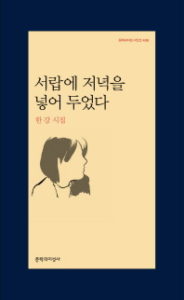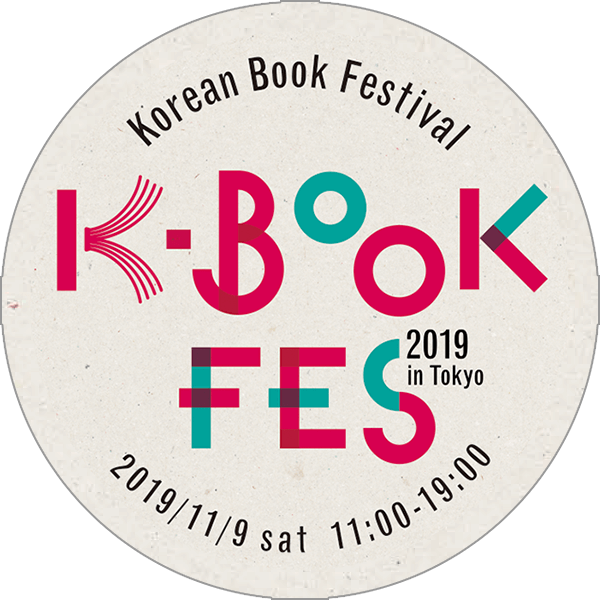世界的に権威のある文学賞の1つ、イギリスのブッカー賞の候補に、韓国人として初めて韓江(ハン・ガン)の『菜食主義者』がノミネートされました。『日本語で読みたい韓国の本-おすすめ50選』第3号では、韓江の詩集『引き出しに夕暮れをしまいこんだ』を紹介しています。哀しみに敏感な視線と、日常の些細なことに美しさを感じ取る感受性で詠まれた詩集です。
●本書の概略
本書は言葉と対峙する作家、ハン・ガンによる初の詩集だ。詩で 文壇デビューを果たした彼女だが、これまでは小説やエッセイを主な 表現の場としてきた。「何よりも切実な問題を書こうとしている」と述 べる著者の作品にはいつも、深刻で、苦しくて、悲しくて、のたうち まわる人間の傷が鋭いナイフで切り出され、その結果として生じた傷 跡=模様が提示されてきた。だが本書は、そうした登場人物の傷だ けを表現した詩集ではない。生に対してひときわ敏感で繊細な著者 の哀しみ、作品を生み出す際の魂を切り刻むような悶絶、作家では なくひとりの母親としての細やかな愛情など、著者自身の独白を聴く ことができる。言葉に苦しみ、言葉と闘い、言葉で解決したいとい う著者にとって、 言葉は魂にも等しい存在であるはずだ。著者の魂 が散りばめられた、これまでの作品と一味違うハン・ガンの世界を堪能できる一冊である。
●試訳
「車椅子ダンス」
涙は もう習慣になりました
でもそれがわたしを完全に飲み込むことはありませんでした
悪夢も もう習慣になりました
いく筋にもわかれ全身の血管に 燃え広がる不眠の夜も
わたしを完全に打ちのめすことはできません
見てください わたしは踊っています
燃え立つ車椅子の上で 肩を揺らしています あぁ、激しく
どんな魔術も 秘法もありません
ただ、いかなるものもわたしを 完全に破壊できなかっただけ
見てください わたしは歌っています 全身で燃え立つ車椅子
見てください わたしは踊っています 全身で火を噴く車椅子
どんな地獄も 罵りと 墓 あのひどく冷たい みぞれも、刃のような 雹の欠片も
最後のわたしを打ち砕けなかっただけ
見てください わたしは歌っています あぁ、激しく
火を噴く車椅子 車椅子ダンス
(22頁、CLONカン・ウォルレの公演に寄せて)
「曉(ヒョ)へ、2002年、冬」
海が僕のところに来なかった。怯えた顔で 子どもが言った
押し寄せてくるから、遠いところから 押し寄せてくるから
わたしたちの体を通り過ぎて ずっと
満ちあふれ続けると思ったようだ
海があなたのところに来なかったの
でも また押し寄せはじめるときは
また果てしなく感じられるでしょう
わたしの脚を抱き寄せ 後ろに隠れるでしょう
まるでわたしが いかなるもの、
海からさえあなたを 守ってあげることができるかのように
咳がひどくて 食べたものを吐き出しながら
涙を流しながら ママ、ママと呼んだように
まるでわたしに それを止めてあげる力があるかのように
でもすぐに あなたも分かるようになるでしょう
わたしができることは 覚えていることだけだということを
あのきらめく巨大な流れと 時間と 成長、
執拗に消失し 新たに生まれるものの前に
わたしたちが共にいたということを
色とりどりの卵のような瞬間の数々を
共に抱いた時代の密やかさを 最初から砂でこしらえた
この体に刻み付けることだけだということを
だいじょうぶ まだ海はやって来ないから
わたしたちを掃き出すまで
わたしたちは こうして並んで立っているから
白い石と貝がらを もっと拾うから
波に濡れた靴を乾かすから ざらつく砂をはたきながら
ときには 座り込んで 汚い手で 目をぬぐったりもしながら
(73〜74頁)
「鏡の向こう側の鏡4――皆既日食」
考えたかった (まだ血まみれで)
太陽より400倍 小さな月が太陽より400倍 地球に近いために
月の丸が 太陽の丸と正確に重なる奇跡について
黒いコートの袖に落ちた雪片の正六角形、
1秒 または更に短く その結晶の形状を見守る時間について
わたしの都市が 鏡の向こう側の都市に重なる時間
燃え立つ 紅い縁だけ残す時間
鏡の向こう側の都市が
つかの間 わたしの都市を貫通する (熱い)影
向かい合う2つの瞳が丸く互いを隠す瞬間 完全に凝視を絶つ瞬間
氷の森閑とした角
(まだ血まみれで) 短く凝視する冬の外炎
(102頁)
●日本でのアピールポイント
日本では『菜食主義者』でその名を知られているハン・ガン。 著者 が紡ぎだす世界に登場する人物はみな、読みながら同情してしまうほ ど不幸だったり、狂気の中から抜け出せないまま終末を迎えたりと、 とにかく壮絶な人生を読む者に突きつける。常に切実な問題や生の 深淵を繊細な感性で見つめ、切り取り、言葉という形で読者に提示 してきた著者だが、普段はささやくような話し方と、はにかんだ笑顔 が印象的な心優しい女性だ。本書を読むと、あの儚げな少女のよう な著者の内面から、凄絶な作品群がどのように生み出されるのかが 見えてくる。哀しみにとても敏感な視線、私たちが日常で見逃しがち な些細なことにも美しさを感じ取る感受性、息子に対する無尽蔵の 愛、作品を生み出す際の血を吐くような苦しみ、それでも言葉と闘 い続けるという決意。小説からはうかがい知ることのできない、たお やかだが芯が強く、熱いけれど冷たい、ひとりの人間としての著者の 精神世界を存分に堪能できる一冊。ぜひ、彼女の小説やエッセイと 併せて読んでもらいたい。