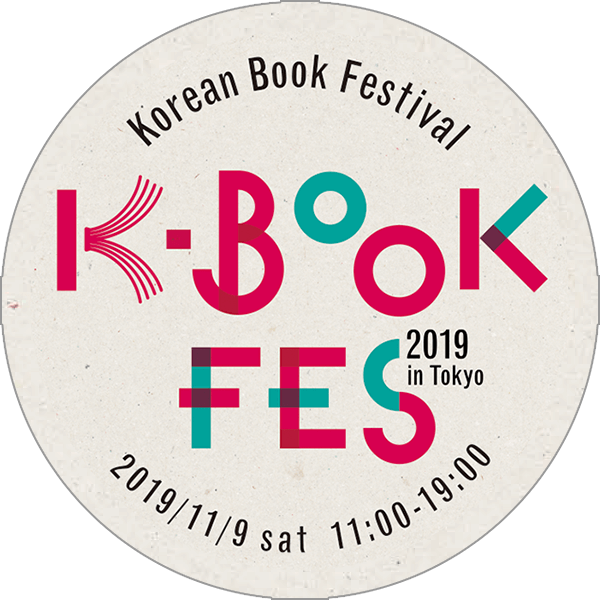生き延びた者をやましさから解き放つ 作家 星野智幸
親しい人を自殺で失った自死遺族は、多くの場合、なぜ自分は止めることができなかったのか、危機のサインを必死で出していたのに気づいてあげられなかったのではないか、などと、強い自責の念にかられる。そして、自分を責めすぎて無能感に取り憑かれ、その人も希死念慮(死にたい衝動)を抱いていく。自死遺族に潜在的に自殺の危険性が増すのは、そのような心の動きによる。
自殺の場合だけではない。東日本大震災で家族を失った人の中にも、そのような人は少なくないだろう。あのとき自分がこうしていたら家族を救えたんじゃないか、と、あれこれ考えては、そうしなかった自分を非難し、生き残ってしまったことにやましさを覚え、次第に死にたい気持ちを募らせていく。
これは誰の身の上にも起こりうることなのだけれど、難しいのは、その自責の念を共有できる人があまりにも少ない、というか、自責している状態のときには理解者は皆無に思える、という点である。破ることのできない孤独に閉じ込められ、自死へと向き合うほかなくなるのである。
韓国文学史上の傑作であるハン・ガンの『少年が来る』は、生き残った者たちの「やましさ」「後ろめたさ」「自責の念」を、丁寧に描いた作品である。扱っているのは、韓国の歴史でも最もおぞましく暗い出来事の一つである光州民主化抗争の虐殺と、その後の抑圧。市民が抵抗した最後の晩に行方のわからなくなった少年の運命を軸に、その晩に少年と関わりながら生き延びた者たちのその後の時代の苦しみを描く。実在の事件を基にしており、現場で起こったことは読んでいて押しつぶされそうになるほど重いが、小説の主眼は、本当の傷は事件の終わった後から広がり、人の心を蝕み、人生をじわじわと破壊していく様子に置かれる。なぜなら、事件は歴史の上でなかったことにされているから、そこで死んだ者たちもいないことになり、事件の記憶、死者の死んだことの記憶は誰とも共有できないからだ。その「傷」こそが、生き残った者たちの、誰とも分かち合えないやましさであり、自分を殺し続ける孤独の毒なのだ。
私は何度目の再読でも泣くことを避けることはできないでいるが、それは震災の現在が、光州民主化抗争のサバイバーたちの苦しむ姿を通じて、私に迫り、私を苛むからだ。私たちはずっと死者とともにいるはずなのに、それが消され、いなかったことにされ、死者の消去こそが前に進むこととされている限り、このやましさから解放されることはなく、私たちは死に引き寄せられ続ける。そんな現在の感触を知るためにも、必読の文学だ。(『ちぇっく CHECK』VOL.2掲載)
『少年が来る』ハン・ガン/著 井手俊作/訳 クオン