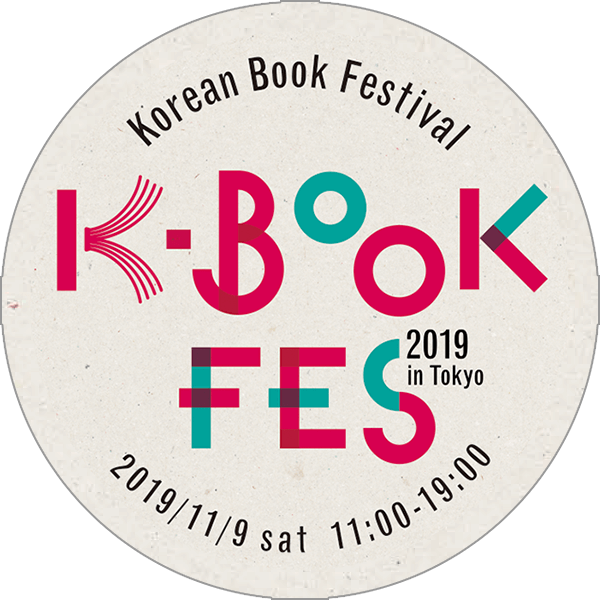韓国近代文学史において初の近代長編小説とされている『無情』。著者の李光洙(イ・グァンス)は、明治学院、早稲田など日本への留学経験もある独立運動家で、多くの小説を残しています。「近代文学の祖」という栄誉を受けながらも、「香山光郎」と創氏改名して日本語小説を発表したことで、「親日文学者」の烙印を押されました。
『無情』は、新聞の連載小説として生まれ、1917年元旦から6月14日まで「毎日申報」に連載されました。李光洙は、植民地朝鮮の近代化と独立を志し、民族が生き残るための希望を抱いて『無情』を書きました。
『李光洙―韓国近代文学の祖と「親日」の烙印』(波田野節子著 中公新書)に、『無情』に込めた李光洙の思いについて、本人の日本語による回想文があります。
 「『無情』を書いた頃のことを、李光洙は次のように日本語で回想している。
「『無情』を書いた頃のことを、李光洙は次のように日本語で回想している。
当時は韓国が日本に併合されて間もないころで、言論出版の自由は露ほども許されていませんでした。それで朝鮮人は、併合直前に一時さかんであった政論さえもできず、固く口はつぐみ、筆は深く、深くおさめられて、死のような沈黙は永遠に、永遠につづくのかと思われました。
かかる時において、沸きかえる脳中の不平と、あからさまには口に出して言えぬ民族的のある憧憬とを、文学的形式を借りて表現しようとするのは、むしろ当然でありましょう。(『朝鮮思想通信』1929年)」
李光洙は「文学によって生への欲望を読者の心に吹き込もうとした」(同書105頁)のです。 
これまで亨植は、決して遊びで善馨を愛したこともないし、肉欲で愛したこともなかった。彼は、自分の同胞が愛を遊びや戯弄とみなす態度について、大きな不満を持っている。自分の一時的な情欲を満足させるために異性を愛することを、大きな罪悪だと見なしている。彼は、愛というものが人類のすべての精神作用のなかで、もっとも重大でもっとも神聖なものの一つであると信じている。だから善馨に対する自分の愛は、自分にとってはきわめて意味深く神聖なものだし、自分の同胞にとっては精神的な大革命だと考えている。亨植の愛に対する態度は宗教的に真摯で、敬虔なものであった。愛を人生の全体とまでは考えないにしても、愛に対する態度によって、人生に対する態度をゆうに決定しうると信じていた。ところがいま考えてみると、善馨に対する自分の愛はあまりに幼稚だった。あまりに根拠が薄弱で内容が貧弱だった。
亨植は今夜そのことに気づいた。そして悲しかった。自分がこれまで人生のすべてを注ぎこんでやってきた事業が虚しいものであったことに、ある日突然気づいたような失望を味わった。同時に、自分の精神の発達程度がまだきわめて幼稚であることにも気づかされた。自分はまだまだ人生を悟ることもできないし、愛を云々するときでもないことに気づいた。今日まで多くの学生に文明を教え、人生を教えていたことがひどく僭越であったことにも気づいた。自分はまだ子供だ。大人がいない社会にちょうど居合わせたから大人のふりをしていたのだ、と気づいて恥ずかしくなる。
亨植の考えは次から次へと続く-。
僕は、朝鮮の進むべき道を明確に知っていると思っていた。朝鮮人が抱くべき理想と教育者がもつべき理想を、確実に把握したと思っていた。しかしこれも畢竟、子供の考えに過ぎない。僕はまだ朝鮮の過去を知らず、現在を知らない。朝鮮の過去を知ろうとすれば、まず歴史を見る目を養い、朝鮮の歴史を詳しく研究する必要がある。朝鮮の現在を知ろうとすれば、まず現在の文明を理解し、世界の大勢を見きわめ、社会と文明を理解するだけの眼識を養ったのちに、朝鮮の現状を緻密に研究せねばならない。朝鮮の進むべき方向を知るのは、その過去と現在を十分に理解したあとのことだ。そうだ、これまで僕が考えてきたことや、主張してきたことは、すべて幼い子供の行為だ。
(中略)
そうなのだ。だから僕たちは学びにいくのだ。君も僕もみんな子供だから、遠く遠く文明の国へと学びにいくのだ。亨植は、隣の車室にいる英采と炳郁のことを考えた。「可哀相な娘たち!」と思った。(『無情』 波田野節子訳 平凡社)より