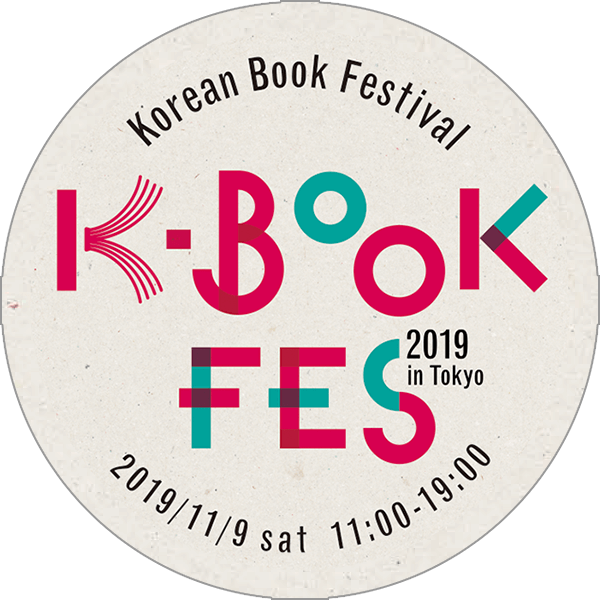出会いや別れ、再会、愛、挫折、喪失、感情の機微を描いた短編集『우리는 페퍼로니에서 왔어(わたしたちはペパロニから来た)』の著者キム・グミさんのトークイベントが7月2日、チャンビ釜山で開かれました。「4人4色 小説トーク」第3弾で、進行は文芸評論家のハン・ヨンインさんです。
キム・グミさんは釜山で生まれ、幼いころ仁川に引っ越しますが、お父さんの故郷である釜山は独特の方言も含めてとても親しみのある場所だと話していました。人生で一番古い記憶も釜山でお母さんがトッポッキの店を営んでいたときの一場面だそうです。以下、対談の一部をご紹介します。


Q. 収録作「クリスマスには」で釜山を舞台に選んだ理由は?
A. 釜山ビエンナーレの出品作として釜山の話を書くことになった。書くにあたって釜山を訪問したが、事前にSNSで「お気に入りの飲食店を教えてほしい」と呼びかけたところ、たくさんの反応があった。それらの店を回りながら構想を練り、いくつかは実際に物語にも登場させた。「(出身地である釜山に)恋しい気持ちはあるが、つらい記憶があるので帰ってきたくない場所だ」という登場人物の台詞がある。私も釜山に対していろいろな感情があるが、そのような気持ちが自分の中にもあったのではないかと思う。
Q. 本書のあとがきに、収録作はいずれも40代で書いた、40代になって変化があった、それによって「人生の春と夏にあたる時期」を振り返ることができるようになった、と書いてあった。40代になってどういうことが変わったか。
A. 発表できる紙面があることがうれしくて、これまでオファーはほぼ断らずに書いてきた。だが40代になって、今までになかった身体の症状が出てきたり、「時に立ち止まって振り返らない作家はいない」という先輩作家の言葉を目にしたりして、今は少し立ち止まっている。40代になってあまり腹を立てなくなった。以前は自分の嫌いな世界と自分が対峙している感覚があったが、今は嫌いな世界と自分が一体になった感じがする。嫌いな世界であれ好きな世界であれ、その中に自分が存在しているという感覚で書くようになった。
Q. 「우리가 가능했던 여름(わたしたちが可能だった夏)」には「心の形質」「生長の時期」という表現が出てくる。作品のキーワードではないかと思った。「形質」や「生長」は話し言葉ではあまり使われない、硬いイメージの単語だが、この小説の中では違和感なく、観念的でもなく、正確な意味をもって伝わってくる。見えないはずの心に「形質」という言葉を使うことで心が可視化され、より明瞭になる気がする。そのためか、敗北感や鬱憤、不安、無気力といった感情が明確に伝わってきた。主人公がある場所を訪ねて過去を振り返る物語だが、どういう思いで書いたか。
A. 大人になること、「生長」することは美しいことばかりではない。私にも過去を振り返って、まるごと切り取ってしまいたい時期もある。たとえば大学時代はうまくいかなかったことやそれによる傷もあり、卒業後何年かは大学に近づきたくなかった。でも40代になって振り返ると、当時はそれなりに「生長」していたのではないか、思うようにいかなかったこともベストを尽くした結果ではなかったか、と思うようになり、そういう観点で書いた。
Q. キム・グミさんの作品には絵画や演劇、舞踊、インスタレーションなど多様な芸術が溶け込んでいる。小説を書くうえで芸術からインスピレーションを受けるほうか。
A. 深い造詣があるわけではないが、芸術には小説を書きたくなる原石のようなものを感じることがある。その原石に自分なりの色をつけて小説を書くと言いたいことをより具体的に伝えられる感じがするので、芸術を取り入れることが多い。小説家も一種の芸術家だが、小説家についての小説は書きたいと思わない。小説家以外の芸術家を登場させるほうが自由に語ることができる。

続いて参加者とキム・グミさんによる朗読や質疑応答の時間がありました。『わたしたちはペパロニから来た』は『센티멘털도 하루 이틀(センチメンタルも毎日だと)』、『あまりにも真昼の恋愛』(すんみ訳/晶文社)、『체스의 모든 것(チェスのすべて)』、『나는 그것에 대해 아주 오랫동안 생각해(わたしはそれについてとても長いあいだ考えている)』、『오직 한 사람의 차지(たった一人のもの)』に続く5作目の短編集です。ほかにもキム・グミさんは長編『경애의 마음(キョンエの気持ち)』『복자에게(ポクチャへ)』を発表するなど旺盛な創作活動を続け、申東曄文学賞、若い作家賞、現代文学賞、金承鈺文学賞などを受賞しています。(文・写真/牧野美加)