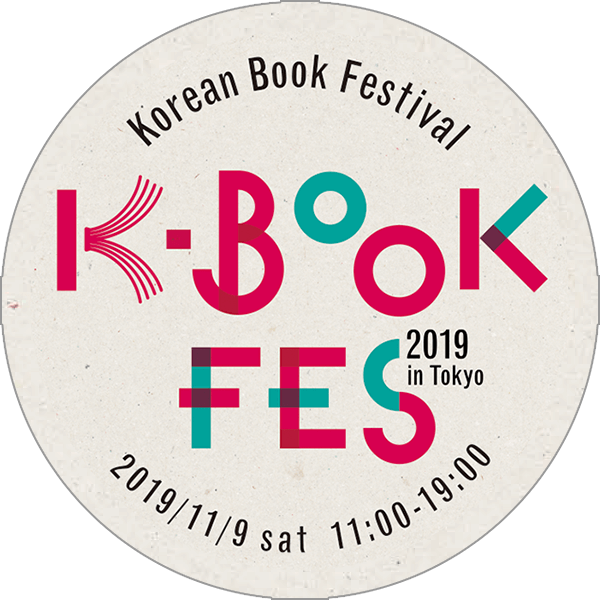K-BOOK FESTIVALでのトークイベントも大盛況だったイ・ギホさん。穏やかでユーモラスな語り口が印象的でしたが、実はちょっと変わった作品を書かれる作家さんで、韓国では「文学界の異端児」の異名を持っています。数々の文学賞を受賞し、大学の文芸創作科の教授でもある彼が「異端児」と呼ばれる理由はどこに隠されているのでしょうか──『原州通信』(清水知佐子訳、クオン)を中心にその謎を探りつつ、文学観や最新作、韓国文学の未来についてもお話を伺いました。
従来の文学といかに距離をとるか
── 本日はよろしくお願いいたします。『原州通信』でまず印象的だったのは、語り手であり主人公でもある「ぼく」が、なんとも卑屈で弱々しく、一言で言えば「どうしようもないやつ」であることです。保身や見栄のためのちょっとした嘘や言動で、どんどんみじめな状況に追い込まれていく。しかも、その「ぼく」は明らかに作家イ・ギホに重ねられています。自分自身を対象化し、引いた視点から滑稽に描いてみせた意図はどこにあったのでしょうか。
『原州通信』は作家としてデビューして5年ほど経ったころの作品ですが、当時の韓国文学は社会的な問題意識に貫かれた真剣な小説が多く、ユーモアがないように感じていました。作家としても、何か深みのある発言をしなければならない雰囲気があったのです。しかし、私自身はそういう人間ではなかった(笑) 私の周りの友達や後輩たちは、どちらかというと『原州通信』の人物たちに近かったんですね。従来の作家との差別化という意味でも、作家として真実を表現するという意味でも、そうした「取るに足らない」人物を描く必要がありました。自伝的な要素を混ぜたのも、オートフィクション的な方法意識が明確にあったというよりは、素朴に卑近なことを書こうとした結果です。
── 方法意識ということで言うと、実在する大御所作家を作品に登場させる手法についてもお伺いしたいです。『原州通信』には、原州に長く住んでいた作家・朴景利が重要なモチーフとして登場します。朴景利の代表作である大河小説『土地』の世界観を再現した高級クラブ、という冗談のような設定ですが……。
なんと説明したらよいか……もちろんメタフィクション的な方法は意識していましたが、しかし意図はもう少し込み入っています。自分より前の作家に対する複雑な距離感を表現したかったのです。たとえば作家であるイ・ギホの住む街に大江健三郎が引っ越してきたとします。私は彼をとても尊敬していますが、しかし私の文学は大江健三郎の文学とは異なります。韓国の伝統文学を象徴する朴景利先生と、その近くに住むイ・ギホの関係もこれと同じ。イ・ギホは朴景利の伝統的な文学に従う気がない。しかし朴景利という人の作家精神や生き方にはすごく共感するし、尊敬している。そうした微妙な距離感が、『原州通信』には総合的に反映されているのです。タイトル自体も朴景利先生のエッセイから拝借しています。

『土地』の著者、朴景利
── 「ぼく」が想像のなかで朴景利に「まだそんなに言い足りないことがあるんですか……」と語りかけるシーンがありますし、ラストでも「なぜ長く書き続けるのか」という朴景利への問いが反復されますね。「作家」の象徴として朴景利を引き合いに出したということでしょうか。
朴景利先生を例に、作家という存在が経験する寂しさや孤独について書きたかったのだと思います。朴景利先生が私の家の近所に引っ越してきたのは事実ですから。実際に何度かベルを鳴らしたこともあります。
── ピンポンダッシュのシーンは実話だったんですか(笑)
そうです。あの作品は、朴景利先生に送る手紙のようなものでした。後々お目にかかれた際に「読みました」と言っていただけたのですが、特に感想などはいただけず。先生はただ苦笑いなさっていただけでした(笑)
疎外された灰色の故郷「原州」
── 『原州通信』の舞台である「原州」は、イ・ギホさんの出身地でもあります。2014年に7人の作家によるアンソロジー『그 길 끝에 다시(その道の果てに再び)』のなかで「原州通信2」という作品を発表していますね。そこで「原州は大切な原風景としての故郷ではなく、好きでもないのに居着いてしまった場所」といったことを書かれたそうですが、改めてイ・ギホさんにとって、原州とはどのような場所なのでしょうか。

『그 길 끝에 다시』ハム ・ジョンイム、イ・ギホ、ほか著、바람、2014年
私の生まれ故郷ではありますが……なんとも特徴のない街です。学生のころは本当に原州が嫌いでした。米軍の基地があったせいで軍事的な文化が都市全体を覆っていて、韓国現代史のひとつの側面を体現している場所です。大学でソウルに出て作家になってから、改めて原州という都市について考えるようになりました。私が感じたのは、そこが韓国の疎外された若者たちを象徴する都市だということです。力のない、弱者の街。色でたとえるなら灰色です。
── 『原州通信』で描かれる原州は、確かに寂れたニュータウンという印象でした。今もそれは変わらないのでしょうか?
今は違いますね。2010年に米軍が去ったことで大きく変わったと思います。産業団地が建てられ、ナイトクラブもたくさんできて若返りました。朴景利先生の住まいが文化的なレジデンスとして活用されるようになり、若い芸術家がたくさん集まるようになりました。創作のための空間が増えたことで、都市の雰囲気ががらっと変わりました。今や韓国の芸術家にとって、ちょっとした憧れの街になっているようです。……だから、今は原州について書きません(笑)
── ある意味、『原州通信』は当時の貴重な証言になったわけですね。
歴史小説ですね(笑)

「精神的勝利」という病
── 『Axt』という媒体のインタビューのなかで、現代の人びとの傾向として「苦痛が襲ってきても、苦痛を苦痛として受け止めないでおこう。苦痛が襲ってきても笑い飛ばそう」といった「精神的勝利」によって現実をやり過ごそうとする態度があるということをおっしゃっていました。「抵抗しないことによって抵抗する」という姿勢は、まさに『原州通信』の「ぼく」そのものです。この「精神的勝利」は必ずしもポジティブな言葉ではないと思いますが、どのような意味が込められているのでしょうか。
多くの韓国の若者がいま、現実にそのように対処しているように思います。彼らは、自分が経験している苦痛が何なのかすらわかっていない。悲しみとは何か、苦しみとは何かということがわからないまま、傷ついているということにすら気づいていないように見えます。その原因に対して抵抗するにしても順応するにしても、まずはその感情を自分で認識する必要があるのです。『原州通信』の主人公だけでなく、他の作品に登場する人物にしても言えることですが、彼らは物語を通じて考え方や行動が変化するきっかけを得ます。それでようやくスタートラインなのです。
── 自覚なく傷ついた状態から、その傷を自覚してスタートラインに立つまでを描く。そのために主人公が平凡である必要があるのかもしれません。ちなみにイ・ギホさんは、そのような「若者」たちを誰の目線から描いているのでしょうか。
書いた時期によって、書き手としての視点も異なります。『原州通信』のときには、主人公の年齢を通り過ぎたばかりの兄のような目線で書きました。最近の作品の語り手には、より自分に近いイメージで、自分を客観視するように書いているものもあります。

韓国文学の未来について
── 韓国の小説界には今、若い作家たちが次々と登場していると思います。日本でも少しずつ紹介が始まっていますが、彼らについてはどのように思われていますか。
若い作家たちからは、本当にたくさん勉強させてもらっています。彼らは、私が知らなかった感情を描き、私には書けない文章や文体を駆使しますから。それを読んで時に心を痛め、時に驚愕します。
── 注目している作家はいますか?
たくさんいますが……たとえばチョン・ジドンという作家です。彼は、従来の小説では見られなかった技法を使います。たとえば文字を拡大したり縮小したり、絵文字を採り入れたり、脚注がそのまま語りになっていたり……小説の途中に絵が出てくる作品もあります。単に突飛な技法を使っているというわけではなく、それが小説の内容としっかり合致していて、これまで描かれてこなかった真実や欲望を表現している。日本でも紹介されることになるだろうと思いますし、そうなったらぜひ読んでみて欲しいです。
── イ・ギホさんは大学でも文芸創作を教えられています。特に「ジャンル小説」(特定のジャンルに依拠したエンターテインメント小説)を書きたい学生が増えていると伺いました。
多いですね。私自身がジャンル小説を教えているわけではないけど、書こうとする学生を止めることはしませんし、むしろサポートするために一緒に勉強しています。ただ、ジャンル小説を書くことを積極的に勧めてはいません。私は、あくまでも純文学を教えるために教員になっているので。
── ジャンル小説について、ポジティブともネガティブとも言えないようですね。
複雑ですね。ジャンル小説と純文学の境目はもともとはっきりしていましたが、最近は境界が崩れつつあります。私としてはもっと崩す方向に向かって欲しいし、そこから新しいものが生まれて欲しいと考えています。しかし、残念ながらジャンル小説の読者たちはそれを望んでいない。彼らはそのジャンルを楽しむために小説を読んでいるので、当たり前ではあるのですが。
── なるほど。ジャンル小説への期待もありつつ、ファンダムへの自閉には複雑な思いがあるんですね。
私の考える文学の核心は、読者がそれまで持っていた規範や先入観を裏切ることです。しかし韓国のジャンル文学は、現状それと正反対の方向に進んでいるように見えます。読者の視線を意識して、その望みに逆らわないように動いているように思える。それについてはネガティブですね。

フェミニズムに対して、男性作家として思うこと
── 既存の規範を裏切るのが文学の核心、というお話がありました。いま日本で韓国文学が盛んに受容されている背景のひとつには、フェミニズムに対する関心の高まりがあります。ストレートに「フェミニズム文学」として紹介されるものだけでなく、広く従来の規範に懐疑を突きつける作品が歓迎されているように思えますが、そうしたフェミニズムの文脈に対してイ・ギホさん自身がどのような考えを持っているかをお聞かせください。
私個人は、男児の誕生を喜ぶ韓国の旧来の価値観で育った世代です。とはいえ私は文学が好きでした。文学には、女性を卑小なものとして扱ったり、男性性を善としたりする価値観はあからさまには描かれません。だから、自分は男性中心主義的な価値観に染まっていないと、数年前までは思っていました。しかし、次第にフェミニズムの議論が活発になるにつれ、私も自分のなかに無意識に潜んでいた男性主義的な価値観に気づくようになりました。『原州通信』を例にあげると、男性の語り手である「ぼく」の使っている語彙や言い回しのなかには、男性中心的で女性を下に見る表現が入り込んでしまっている。この作品を書いた当時の私は、そのことに気づけていませんでした。私は作家でありながら、社会の雰囲気に便乗して、そのような価値観を肯定してしまっていたのです。フェミニズムに触れなかったら、私は変わらずにそんな作品を書き続けてきたと思います。
── 確かに、『原州通信』の「ぼく」には──もちろんそこに重ね合わされた作家自身の自己批判が効いているとはいえ──いわゆる弱者男性の開き直りのような要素がありますね。
言語には無意識の価値観や慣習が反映されています。たとえば、韓国語で「両親」は“부모(父母)”と書きます。英語のparentsには性差がないのに。もっと言えば男性が先という認識もそこに入り込んでいます。だから言葉の芸術である文学からフェミニズムが始まるのは、ごく自然なことなのではないかと思うのです。
── 実際に、そうした問題意識を踏まえてお書きになった作品はありますか?
最近、女性が語り手となる作品を書き始めました。自分の言語的な習慣を、意識的に検証しようと思ったのです。それまでの私の作品は、語り部がほとんど男性でしたから。語り部の選択に慎重になることで、ちょっとした語彙の選択にも自覚的になる気がします。
── 男性自身が男性を対象化することもフェミニズムの文脈において重要だと感じますし、その観点からイ・ギホ作品を読み解くこともできる気がしていましたが、そこに女性視点という新しいチャレンジが加わるのは非常に楽しみです。来年、日本で新たに2作品──『誰にでも親切な教会のお兄さんカン・ミノ』(斎藤真理子訳、亜紀書房)、『舎弟たちの世界史』(小西直子訳、新泉社)が紹介されますが、最後に日本の読者にメッセージをいただけますか。
あまり読者に対して直接メッセージを伝えることはないんですが……(笑) そうですね、私の作品の登場人物たちは、とても平凡で取るに足らない存在です。そのような生き方にも価値や意義があるのではないか、ということを私は伝えたかったのです。私の本を通じて、それを一緒に悩み、考える時間をつくれたらと思います。ありがとうございました。
(インタビュー:松本友也 ステージ写真:KAI-YOU 新見直)
プロフィール
-
イ・ギホ
1972年、江原道原州市生まれ。明知大学大学院で博士課程を修了。
1999年『現代文学』に短編「バニー」が掲載され文壇デビュー。
その後2010 年に李孝石文学賞、2013年に金承鈺文学賞、2014年に韓国日報文学賞、2017年に黄順元文学賞を受賞。
現職は、光州大学文芸創作科教授。
最新作に『モギャン面放火事件顚末記—ヨブ記43 章』(現代文学)がある。 -
松本友也(まつもと・ともや)
1992年生。都市文化批評誌「Rhetorica」で企画・ライティングを担当。
直近の仕事は、都市リサーチ報告書『ARTEFACT#02』(慶應アートセンター)、連載「韓国ポップカルチャー彷徨」(KAI-YOU Premium)、座談会「部室・棺桶・公共性」(『クイック・ジャパン 146』)など。
Twitter @matsutom0