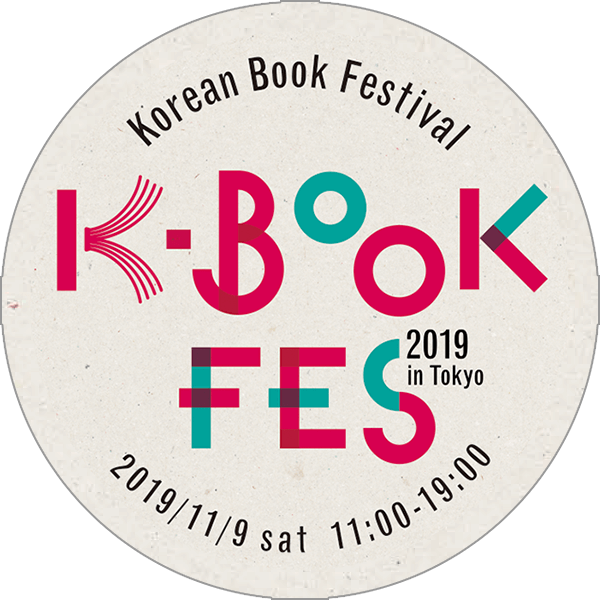【河出書房新社賞】
村上 巳由起さん
柔らかな白に包まれる感触
 そっと静かにささやく声。この小説を読み始めた時に感じたこと。少しかすれたような小さな声で、さまざまな白いものの名前が浮かび上がる。
そっと静かにささやく声。この小説を読み始めた時に感じたこと。少しかすれたような小さな声で、さまざまな白いものの名前が浮かび上がる。
おくるみ、うぶぎ、しお、ゆき、こおり、つき…。
ささやく声は語り続ける。自分が生まれる前に、母がたった独りで産み、二時間後に死なせてしまった姉のことを。
もし姉が生きていたら、自分はここにいなかった。彼女のいた跡に自分が存在し続ける。その痛みを「私」は考える。
(傷口に塗る白い軟膏と、そこにかぶせる白いガーゼのようなものが私には必要だったのだと。)
そう思いながらも自問する。
(けれども、その文章の中へ白いガーゼをかぶって隠れてしまっていいものなのか。)
そして悟る。
(どこかに隠れるなどとはしょせん、できることではなかったと。)
姉への想いが、さまざまな白を通して浮かび上がる。
滞在先の部屋の「ドア」を白く塗る。気がつくと雪がしんしんと降っている。
生まれたばかりの赤ん坊が雪のように真っ白な「おくるみ」にしっかりとくるまれている。
母は陣痛をこらえながら、白いきれで「産着」を縫い上げ、独りで赤ん坊を産んだ。
「タルトック」のように、真っ白で美しかった赤ん坊。
生まれて二時間で亡くなった姉は、一時間ほどして真っ黒な目を開けて母の方を見たという。母の「しなないで しなないでおねがい」という言葉を見つめていた。
自分はこの世に生まれてきて良いのだろうかと問いかける小さな命。不安な思いが募りかけた時、ささやき声が耳に届く。
しなないで しなないでおねがい。
この世に存在して良いのだと、求められているのだと確信し、安心してこの世を去った姉。
そんな想像をしながら、亡くなってしまった彼女の目を通して、「私」が紡ぎだす白いものたちの物語を受け止める。
ヨーロッパで唯一、ナチに抵抗して蜂起した都市に滞在し、「私」は彼女になって街を歩く。その街で見たもの感じたことを綴っていく。
また母国での記憶を手繰る。実家の隣りにいた怯えた白い犬。吹雪の日。冬の海辺の砂浜に集まっていた白いかもめたち。
さまざまな白いものたちのイメージが並び、それがそのまま亡くなった姉の経験になり考えになる。「私」が見るものも、まわりに存在し続けるものも、白はすべて彼女であり「私」なのだ。
読後は、柔らかな白に包まれて、身も心も白に染まっていくような感触。清閑な物語だ。