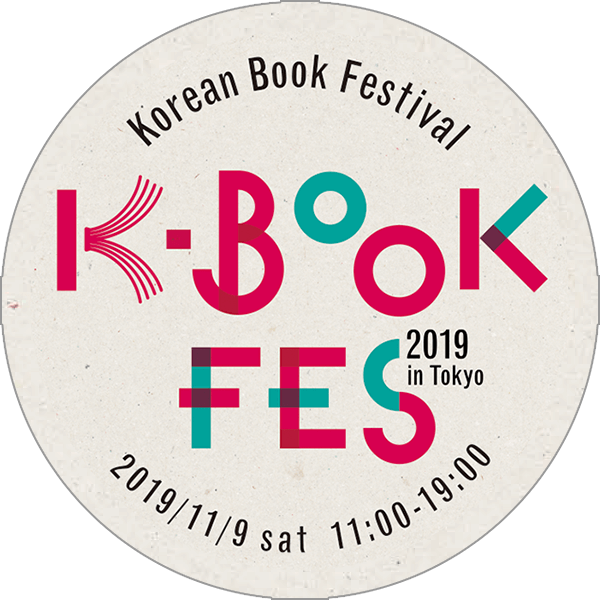【クオン賞】
松本美月さん
いつか見た「痛み」、その後——。
 これは私たちの物語なのだ。読了後、漠然とそう感じた。自分がかつてどこかで感じ、絡まったまま心の隅に放置されていた感情の糸が、ゆっくりとほどかれ、その姿をあらわにする。それは時に残酷であり、おぼろげであり、目をそらすことが出来ない。
これは私たちの物語なのだ。読了後、漠然とそう感じた。自分がかつてどこかで感じ、絡まったまま心の隅に放置されていた感情の糸が、ゆっくりとほどかれ、その姿をあらわにする。それは時に残酷であり、おぼろげであり、目をそらすことが出来ない。
どうしてあの時、あの人からの連絡は急に来なくなったのだろう。なぜあの人に対してあんな振る舞いをしてしまったのか。あの人の心を、どうして受け止めることが出来なかったのか……7編の物語は、私たち人間が他者との関わりとそこで生じた悲しみ・苦しみによって形成されることをはっきりと突き付けてくる。そして、そこで描かれる感情はどれもみな、誰しもがどこかで知ってしまった感情なのである。できれば知りたくなかった、いつのまにか生まれてしまっていた感情が、物語という形を通して、私たちの前に提示される。否応なく、私たちは自らの心を向き合わざるを得なくなる。そこで私たちは思いを巡らせるのだ。自らの悲しみの記憶へ、なぜそうなったのか? あの時自分はどうしてあんなことをしたのか? 今の私ならどうしただろうか? と。
「オンニ、私の小さな、スネオンニ」が忘れられない。かつて親友であったにも関わらず、時代と時の流れによって互いを拒絶するようになった母とスネオンニ。物語の語り手である娘に、病床の母は亡くなったスネオンニが逢いに来たと語る。娘は母の話に疑問を抱くが、スネオンニの遺品にあった二人の写真を見つけた時、二人が長い時を経て心の中で互いを許しあったことを悟る——。
グローバル化が叫ばれ、どんなにネットが広大になったとしても、世界は閉じたまま、互いに触れ合うことがないままである。むしろ、その閉塞感は一時よりも増しているだろう。
だからこそ、この七編の物語にはある「強さ」があるのだと思う。物語の最後、主人公たちは自らの止まっていた時計の針を、そっと、静かに動かし始める。それは他者との関わりと、自らとの対話の果ての行為だ。人生に向き合う、そして再び歩む。その大切さ、尊さを七編の物語は小さな声で、それでもはっきりとささやき続けている。また作者は、人が人を拒絶できるように、またそれを超えて他者を受け入れることが出来ることを決して忘れない。それは私たちがいつのまにか忘れてしまっていたことであり、同時に決して忘れてはならないことである。