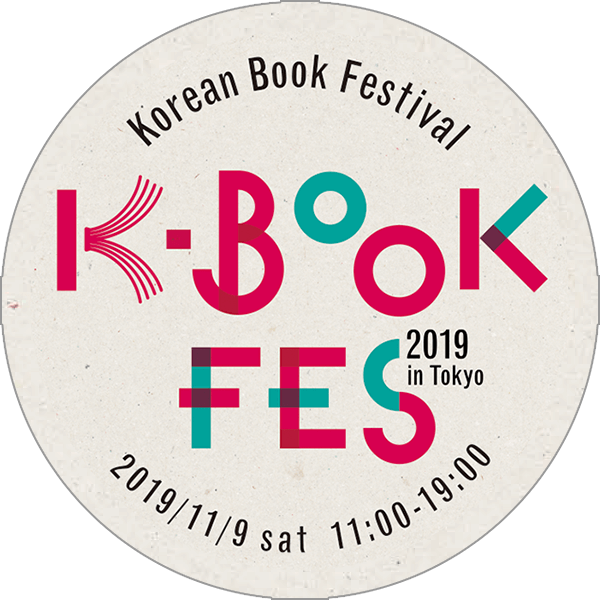出版社チャンビの多目的空間「チャンビ釜山」で「4人4色 小説トーク」というリレーイベントがスタートしました。4人の作家が著書やそれに関連するテーマ(仕事、家族、愛、夢)で司会者と対談するものです。チャンビと釜山図書館の共同主催で、オンラインでも生中継、配信されています。
トップバッターは、働く若者の日常を描いた『仕事の喜びと哀しみ』(牧野美加訳、クオン)でチャンビ新人小説賞を受賞したチャン・リュジンさんです。釜山は両親の出身地でもあり、親しみのある都市だと話していました。
今年4月に刊行された初の長編『달까지 가자(月まで行こう)』(「日本語で読みたい韓国の本」で紹介しています)は、20代後半の女性会社員3人が一攫千金を夢見て仮想通貨に投資する物語です。職場や社会の不条理や差別、格差に耐え、互いに支え合い、涙ぐましいほどつつましく暮らす主人公たちの日常もリアルに描かれています。司会は同書の解説を執筆した文芸評論家ハン・ヨンインさんです。主なやりとりをご紹介します。


Q. この物語はどのように着想したのか。
A. 仮想通貨の第一次ブームだった2017~18年ごろ、まだデビュー前だったが、その現象と人々の反応に強い関心を持っていた。デビュー後、それが頭のどこかに残っていたのか、いつか小説として書けたらと思うようになった。実際に通貨の取引をしたことはない。
Q. 「チャン・リュジン小説」は人物が生き生きと描かれているのが特徴だと思う。人物を書くときに何か意識しているか。
A. 人は誰しもさまざまな面を持っている。小説の中のキャラクターもそうであってほしいので、そのように描くよう心がけている。
Q. もう一つの特徴は読者を物語に没頭させるリアルな「話し言葉」だと思う。良い小説家は良い観察者だと聞くが、普段から人の会話をよく観察しているのか。
A. 「この会話は使えそうだから覚えておこう」などと意識しているわけではないが、無意識に観察しているようだ。小説を書くとき、どんどん筆が進むということはあまりないが、会話文を書くときは楽しみながら没頭して書ける。書きはじめる前の発想の段階で台詞や会話が浮かび、それを生かすために、ある場面や小説を書くこともある。逆に、書いている途中で、思ってもみなかった台詞がふと浮かぶこともある。
Q. この作品には「欲望」に対するジェンダー的、世代的な感覚が溶け込んでいると思う。同じことでも男性が望めば「野望」、女性が望めば「俗物的、虚栄」だと言われる。少し前には金融委員会(国家行政機関)のトップが、若者が仮想通貨市場に熱中することを「正しい道ではない」と発言し問題になった。この作品を書くとき「欲望」をめぐる韓国社会の分断について考えていたか。
A. 世代的なこと、ジェンダー的なことは念頭に置いていた。そのためわざと第3部はあのような構成にした(3人とも投資に成功し大きな利益を手にする)。
Q. ハッピーエンドにしないほうがよかったのではないかという意見もあるが。
A. 最初から結末は決めていて、こういう結末にするために小説を書いた。この3人には、私の小説の中でだけはいい思いをさせてあげたかった。「ハッピーエンド」の小説と言われるが、「ハッピーエンド」という枠だけに押し込めてほしくない。砂糖をまぶしたような甘いエンディングのあとに感じるほろ苦さやすっきりしない気持ちも大切にしながら書いた。そのほろ苦さも小説の一部だと思っている。
Q. 「3人が『自分たちは崖っぷちに立っている』と感じるのは、あまりに主観的なのではないか。客観的に見れば、ソウルに住み、満足のいく額でなくとも毎月給料が入ってくる状況は崖っぷちではない」と感じる人もいるだろう。どう考えるか。
A. 3人が客観的に見て崖っぷちにいるのかどうかは重要ではない。それを判断すること自体が主観的ではないだろうか。「本人がそう感じている」ということが重要だと思う。3人をもっと厳しい状況に置くこともできたが、あえて物語の雰囲気に合うように設定した。
Q. この小説の続編の予定は? 次の作品の計画は?
A. 続編は今のところ考えていない。次回作も具体的な計画はないが、いつか本についての小説を書いてみたいと思ったことはある。売り買いされる「物」としての本。
対談に続いて、参加者と作家本人による本文の朗読と質疑応答の時間もありました。「4人4色 小説トーク」はこのあと、シン・ギョンスク(6/18)、キム・グミ(7/2)、キム・ユダム(7/16)各作家が登壇予定です。(文・写真/牧野美加)