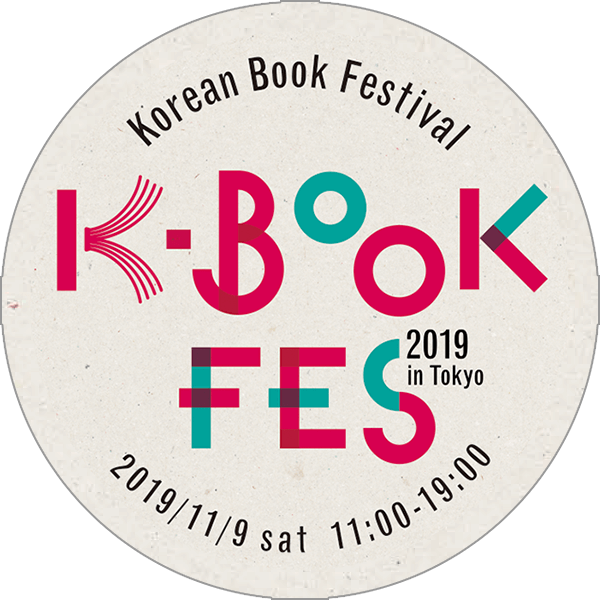紹介——最近の韓国・朝鮮・在日関連図書2
舘野 晳(日本出版学会会員)
今月のレポートでは、SIBF(ソウル国際図書ブックフェア)の視察報告を予定していたが、予期しない事態が発生、ソウル訪問をキャンセルしてしまった。そこで前月に引き続き、人文書を中心に近刊書の紹介をすることにした。
前月も新刊6冊の紹介をしたが、その後も関連図書刊行の勢いはとどまらない。まず、新書版の2冊から。
林典子『朝鮮に渡った“日本人妻”—— 60年の記憶』(岩波新書)は、「フォト・ドキュメンタリー」と銘打ち、報道写真家の著者が北朝鮮各地で暮らす日本人妻を訪ね、暮らしの様子や家族や祖国日本に寄せる思いを聴取している。彼女たちは1959年に開始された「帰国事業」で、朝鮮人の夫とともに北朝鮮の地に渡り、苦難の歳月を送ってきた。政治の荒波に翻弄された渡航後の現地暮らしの体験と心情が、ためらいがちな口調で語られている。そこには声高な政治批判を見いだすことはできないが、読む者を熟考させる内容がたっぷり詰まっている。そして随所に配置された写真が、彼女たちの孤立感をいっそう引き立てて効果的である。
黒田勝弘『韓めし政治学』(角川新書)。在韓40年になる著者の韓国レポート。著者のこの種の本を何冊読んだだろうか。現地で暮らす者の利点を生かし、政治的大状況の分析から民心の機微にいたるまで、その大胆かつ微にわたるユニークな筆遣いを愛読してきた。そして今では著者特有の「イヤミ」にも慣れてしまった。今回は「食」に焦点を絞り、政治的状況と「食」との関係を解いてみせてくれる。いつもながら、やや強引な論の進め方も見られるが、それもまた「黒田節」を読む楽しさなのだと、私は達観している。
喜田由浩『韓国でも日本人は立派だった』(産経新聞出版)。著者は産経新聞文化部編集委員、かつて『北朝鮮に消えた歌声 永田絃次郎の生涯』(新潮社)という珍しい本を出し、興味深く読んだことが思い出される。本書は題名や版元の与えるイメージから、特定(「嫌韓・反韓」)の色彩が濃い内容ではないかと、手にすることを避けたがる読者がいるかも知れない。だが通読してみると、それほど偏向したものではない。日本が朝鮮半島を植民地支配した時代の日本人が関係した事象の数々を収集し、1冊に仕立てたものなので、それらの事実に疎い読者だったら、新たな知見が得られるメリットがあるのだ。問題はそれらの評価(価値判断)であるが、著者は努めて客観的な叙述を心がけている。歴史的事実を単純に「黒か白か」と二分して結論づけるのは正しいとはいえない。多角的な視野から素材を集め、総合的な判断をくださねばならないのだ。それだけに、本書のように「クセのある」本にも目を通して置く必要があるだろう。ただし、個々の事物紹介に割いた紙幅はあまりにも少なすぎる。本書は「営業的(政治的)」観点からなのか、題名や各章のキャプションの表現が意図的なものになっており、それが本書の評価を下げる結果になってしまった。残念なことである。
金善洙(山口恵美子・金玉染訳)『労働を弁護する』(耕文社)。サブタイトルの「弁護士金善洙の労働弁論記」が示すとおり、著者がこれまで担当してきた労働事件の弁護活動を綴ったものだ。全体は25章で、各章がそれぞれの事件報告に相当している。たとえば「8年8か月ぶりの復職」「あまりに稚拙で無謀な労組弾圧」「ある日突然キャンバスから消えた教授たち」「無謀な検察権行使、当然の判決」「10年かかった退職金訴訟」と言う具合である。
著者は全泰壱事件に触発されて弁護士を志し、やがて趙英来弁護士事務所から弁護士活動を開始し、これまでもっぱら労働事件を担当してきた。本書には韓国社会の下積みで苦しむ労働者の状況と、彼らの待遇改善、権利保障のために闘った弁護士活動が具体的に記録されている。日本でも労働裁判は一般社会の認識から遠い領域にある場合が多く、全貌把握がかなり困難だが、韓国ではどうなのか、本書を読んで韓国の経済社会を認識する幅を広げていきたい。
昨年の刊行であるが、浦川登久恵『羅蕙錫』(白帝社)も紹介しておきたい。かなりの韓国通でなければ、羅蕙錫という人物には馴染みがないだろう。朝鮮最初の女性西洋画家で、文筆家でもあり、日本支配下の外務官僚の妻でもあった。彼女は活動や言動の振幅が大きかったためなのか、韓国では厳しい毀誉褒貶の的だったが、最近は周辺研究が進んで、彼女の考えや生き方が受け入れられるようになっている。本書はそうした羅蕙錫再評価の成果を生かしながら、波瀾万丈の彼女の生涯を文学研究者である著者が追跡した評伝である。
韓国フェミニズムの先駆者としても知られるようになった羅蕙錫について、日本でこれほど詳細な調査研究が刊行されたのは初めてであり、韓国の近代女性史研究に対して貴重な資料を提供したことになる。専門研究書の水準を維持しながら、一般読者向けの読みやすさに配慮している点についても指摘しておきたい。
最後に、こちらも刊行からやや日数が経過してしまったが、これまで紹介が抜けていたので、次の5冊を挙げておきたい。
朴裕河『引揚げ文学論序説』(人文書院、2016.11)
柳本芸(吉田光男訳注)『漢京識略——近世末ソウルの街案内』(東洋文庫、2018.2)
渡邊澄子『植民地朝鮮における雑誌「国民文学」』(人文書院、2018.8)
関口すみ子『漱石と戦争・植民地 —— 満州、朝鮮、沖縄、そして芸娼妓』(東方出版、2018.12)
西槇偉・坂元昌樹『夏目漱石の見た中国——『満韓ところどころ』を読む』(集広舎、2019.4)